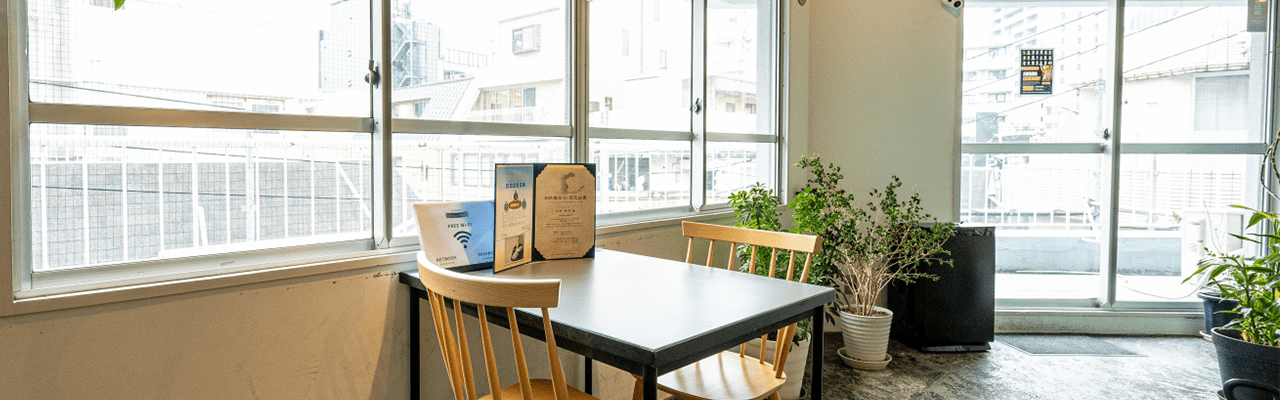
相続セミナー 第11回:遺言書の種類①:自筆証書遺言~手軽さの裏にある注意点~
「遺言書を作った方が良いのは分かったけど、どんな種類があるの?」「自分で簡単に作れる遺言書があると聞いたけど、大丈夫なのかな?」
前回の第10回ブログでは、遺言書がない場合に適用される法定相続のメリットとデメリットについて解説し、改めて遺言書作成の重要性をご確認いただけたかと存じます。【第2部:遺言のすべて - 想いを形にする】では、今回から数回にわたり、具体的な遺言書の種類と、それぞれの特徴、作成方法、注意点などを詳しくご紹介していきます。
まず最初に取り上げるのは、最も手軽に作成できるとされる「自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)」です。その名の通り、遺言者本人が自筆で作成する遺言書ですが、この「手軽さ」の裏には、知っておかなければならない多くの「注意点」や「リスク」が潜んでいます。
この記事を読めば、自筆証書遺言とはどのようなものか、メリットとデメリット、そして作成する際に絶対に押さえておくべきポイントが理解できるはずです。安易な作成で後悔しないために、ぜひ最後までお読みください。
自筆証書遺言とは?~自分で書く遺言~
自筆証書遺言とは、民法第968条に定められている遺言の方式の一つで、遺言者が、その遺言の全文、作成した日付、そしてご自身の氏名を全て自分で書き(自署し)、これに押印して作成する遺言書のことです。
特別な道具は必要なく、基本的には紙とペン、そして印鑑があれば作成できます。公証役場に出向く必要もなく、証人も不要なため、費用をかけずに、ご自身のタイミングで、誰にも知られずに作成できるという特徴があります。
「思い立ったが吉日」とばかりに、すぐに取り掛かれる手軽さが魅力と言えるでしょう。
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言には、以下のようなメリットがあります。
-
手軽に作成できる 最大のメリットは、やはりその手軽さです。紙と筆記用具、印鑑さえあれば、いつでもどこでも、誰の力も借りずに作成を始めることができます。専門家への依頼も必須ではないため、時間的な制約も少ないでしょう。
-
費用がほとんどかからない 公証人に支払う手数料などが不要なため、ご自身で作成する場合、費用は基本的に紙代やペン代程度で済みます。経済的な負担が少ないのは大きな利点です。
-
内容を秘密にできる 作成の事実や遺言の内容を、誰にも知られることなく秘密にしておくことができます。プライバシーを重視したい方にとっては安心できる点です。
-
比較的容易に修正・撤回ができる 遺言者は、いつでも遺言の全部または一部を撤回することができます(民法1022条)。自筆証書遺言の場合、法的に有効な新しい遺言書を作成することで、前の遺言書の内容を変更したり、事実上撤回したりすることが比較的容易です(ただし、変更や撤回も法律に定められた方式に従う必要があります)。
これらのメリットから、自筆証書遺言は最も利用しやすい遺言の方式の一つと考えられています。しかし、その手軽さゆえのデメリットやリスクも少なくありません。
自筆証書遺言のデメリットと注意すべき点
手軽に作成できる反面、自筆証書遺言には以下のような多くのデメリットや注意点があり、これらを十分に理解しておかないと、せっかく書いた遺言書が無効になったり、かえって相続トラブルの原因になったりする可能性があります。
-
方式不備で無効になるリスクが高い 自筆証書遺言が法的に有効と認められるためには、法律で定められた厳格な方式を守らなければなりません。
- 全文の自署: 遺言の本文は、必ず遺言者本人が手書きしなければなりません。パソコンやワープロで作成したもの、他人に代筆してもらったものは原則として無効です(例外として、後述する財産目録は一部自署でなくても可)。
- 日付の自署: 遺言を作成した年月日を具体的に(例:「令和〇年〇月〇日」)自署する必要があります。「〇月吉日」のような曖昧な記載は無効となる可能性が高いです。
- 氏名の自署: 遺言者本人の氏名を自署する必要があります。通称やペンネームではなく、戸籍上の氏名を正確に記載するのが望ましいです。
- 押印: 遺言書に印を押す必要があります。法律上は認印でも構いませんが、本人の意思による作成であることを明確にするため、実印を使用し、印鑑登録証明書を一緒に保管しておく方がより確実です。
これらの要件の一つでも欠けていたり、不備があったりすると、遺言書全体が無効になってしまう恐れがあります。
-
内容が不明確・曖昧で解釈に争いが生じるリスク 法律の専門家ではない方が作成した場合、遺言の内容が不明確であったり、法的に見て複数の解釈ができたりする表現を使ってしまうことがあります。
- 例えば、相続させる財産の特定が不十分(「自宅の土地を長男に」だけでは、どの土地か特定できない場合がある)であったり、相続人の指定が曖昧だったりすると、相続人間で遺言の解釈を巡って争いが生じる原因となります。
-
紛失・隠匿・改ざんのリスク 自筆証書遺言は、通常、作成者本人が自宅などで保管します。そのため、
- 遺言者自身がどこに保管したか忘れてしまい、相続開始後に発見されない。
- 遺言書の内容が自分に不利だと考えた相続人によって、隠されたり、破棄されたり、あるいは改ざんされたりする危険性。 これらのリスクが常に伴います。
-
発見後の家庭裁判所での「検認」手続きが原則必要 自筆証書遺言(または秘密証書遺言)の保管者またはこれを発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません(民法1004条)。
- 検認とは: 遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などが遺言書作成時の状態であることを確認し、その後の偽造・変造を防止するための保全手続きです。遺言の有効・無効を判断するものではありません。
- 検認手続きには、相続人全員に期日が通知され、通常1~2ヶ月程度の時間がかかります。また、戸籍謄本などの必要書類も多く、手間がかかります。
- 封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上で開封しなければならず、勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられる可能性があります。 (ただし、2020年7月から始まった「法務局における自筆証書遺言書保管制度」を利用した場合は、この検認手続きは不要となります。この制度については、後の回で詳しく解説します。)
-
遺言能力を争われる可能性 特に高齢の方が作成した場合など、遺言書作成時に遺言者に十分な判断能力(遺言能力)があったのかどうかが、後日相続人間で争われることがあります。「認知症の状態で書いたものだから無効だ」といった主張がなされるケースです。これを防ぐためには、作成時の状況を客観的に示す証拠(医師の診断書など)を残しておくなどの対策が考えられます。
財産目録の作成方法の緩和(2019年1月施行の法改正)
自筆証書遺言の作成負担を軽減するため、2019年1月13日に施行された改正民法により、遺言書に添付する「財産目録」については、全文を自書しなくてもよいことになりました。
- パソコンで作成した財産目録や、銀行通帳のコピー、不動産の登記事項証明書などを財産目録として添付することができます。
- ただし、この場合でも、財産目録の各ページ(両面に記載がある場合は両面)に、遺言者が署名し、押印する必要があります。
- あくまで財産目録部分の緩和であり、遺言の本文(誰に何を相続させるかなどの意思表示部分)は、引き続き全文を自書しなければなりません。
この改正により、財産が多い場合の作成の手間はいくらか軽減されましたが、遺言本文の自署要件は変わらないため、依然として注意が必要です。
自筆証書遺言を作成する際のポイント
上記のデメリットや注意点を踏まえ、もし自筆証書遺言を作成する場合には、以下の点に留意しましょう。
- 法律で定められた方式を厳守する: 全文自書、日付自書、氏名自書、押印は絶対です。
- 明確かつ具体的な表現を用いる: 誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのか、誤解の余地がないように具体的に記載します。不動産であれば登記事項証明書の記載通りに、預貯金であれば金融機関名・支店名・口座種類・口座番号まで記載するのが理想です。
- 日付は正確に記載する: 作成した年月日を明確に記載します。
- 署名・押印を忘れない: 氏名を自署し、押印します。印鑑は、本人のものであることが明確なもの(できれば実印)を使用しましょう。
- 内容を定期的に見直す: 家族構成や財産状況、気持ちの変化に合わせて、必要であれば書き直すことも検討しましょう。
- 保管方法を工夫する: 信頼できる人に預ける、貸金庫に保管するなどの方法がありますが、最も推奨されるのは「法務局における自筆証書遺言書保管制度」の利用です。これにより紛失・隠匿・改ざんのリスクを大幅に減らせ、検認も不要になります。
自筆証書遺言と行政書士の関わり
「自分で書く遺言」である自筆証書遺言ですが、行政書士が関与できる部分も多くあります。
- 作成に関する相談・アドバイス: 自筆証書遺言を作成したいが、法的に有効なものが書けるか不安、という方に対し、行政書士は法律上の要件や注意点、記載すべき内容について丁寧にご説明し、アドバイスを行います。
- 文案の検討サポート: 遺言者ご本人の意思を最大限に尊重しつつ、その内容が法的に明確で、後日解釈に争いが生じないような文案となるよう、一緒に検討し、サポートします。(ただし、行政書士が遺言本文を代筆することはできません。)
- 財産調査・相続人調査のサポート: 遺言書に記載する財産の内容を正確に把握するための財産調査(不動産調査、預貯金調査など)や、相続人を確定させるための戸籍謄本等の収集は、行政書士の専門分野です。
- 法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用支援: この制度を利用するための申請手続きについて、書類作成のサポートや申請の代行(可能な範囲で)を行います。
- 将来の検認手続き申立書の作成支援: もし法務局の保管制度を利用しない自筆証書遺言で、将来検認が必要になった場合、その申立書作成の支援も行政書士が行えます。
行政書士は、遺言者ご本人が有効な自筆証書遺言を作成できるよう、法的な側面からサポートするとともに、より確実性を求める方には、次にご紹介する「公正証書遺言」の作成サポートもご提案できます。
まとめ:手軽さの裏にあるリスクを理解し、慎重な判断を
今回は、自筆証書遺言のメリット・デメリット、作成時の注意点について解説しました。
- 自筆証書遺言は、手軽で費用もかからず、内容を秘密にできるというメリットがある。
- 一方で、方式不備で無効になるリスク、内容の不明確さによる紛争リスク、紛失・隠匿・改ざんリスク、そして原則として家庭裁判所での検認手続きが必要というデメリットがある。
- 財産目録の作成方法は一部緩和されたが、遺言本文は依然として全文自書が必要。
- 法務局の保管制度を利用することで、一部のリスクは軽減できる。
自筆証書遺言は、その手軽さから安易に作成されがちですが、上記のような多くの注意点が存在します。せっかくの遺言が無駄になったり、かえって混乱を招いたりしないよう、そのリスクを十分に理解した上で、慎重に検討することが何よりも大切です。
「自分で書けそうだけど、やっぱり不安…」「法務局の保管制度って具体的にどうすればいいの?」など、少しでも疑問や不安を感じたら、ぜひ一度、行政書士などの専門家にご相談ください。
次回は、第12回「遺言書の種類②:公正証書遺言 ~安心・確実を選ぶなら~」と題して、専門家である公証人が作成に関与し、最も安全で確実性の高い遺言方式とされる公正証書遺言について詳しく解説していきます。

