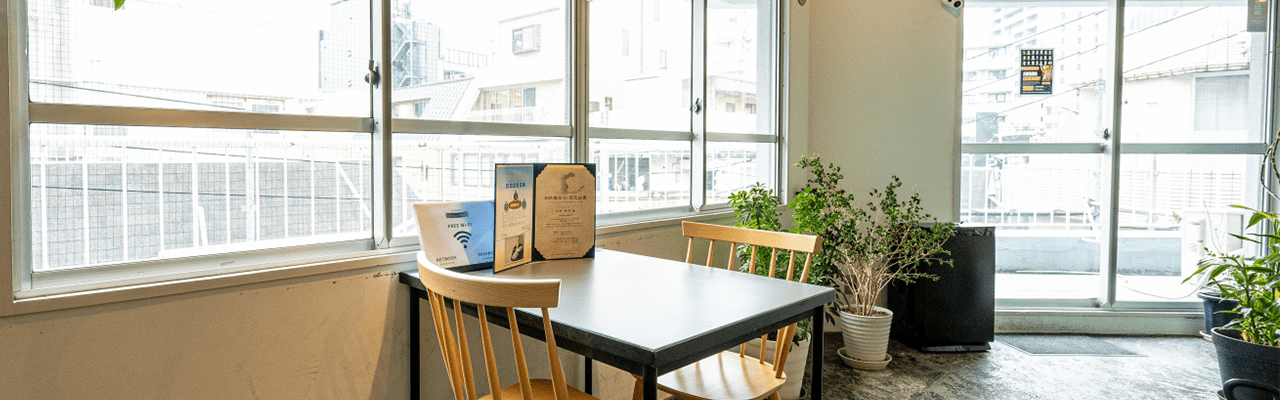
相続セミナー 第12回:遺言書の種類②:公正証書遺言~安心・確実を選ぶなら~
「自分で遺言書を書くのは不安がある…もっと確実で安心な方法はないの?」「手続きが大変でも、法的にしっかりした遺言書を作っておきたい。」
前回の第11回ブログでは、手軽に作成できる「自筆証書遺言」について、そのメリットと共に、方式不備による無効リスクや検認手続きの必要性といった注意点を解説しました。「手軽さ」には、それ相応のリスクも伴うことをご理解いただけたかと思います。
そこで今回は、より安全で確実性の高い遺言の方式として、「公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)」をご紹介します。この方法は、法律の専門家である公証人が作成に関与するため、遺言の有効性が高く、相続開始後の手続きもスムーズに進むことが多いのが特徴です。「安心・確実」を最優先に考える方にとっては、最もおすすめできる遺言の形式と言えるでしょう。
この記事では、公正証書遺言とはどのようなものか、その絶大なメリット、考慮すべき点、作成の手順や費用、そして行政書士がどのようにサポートできるのかを詳しく解説していきます。
公正証書遺言とは?~専門家が作成に関与する遺言~
公正証書遺言とは、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口頭で伝え(口授といいます)、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、遺言書として作成するものです(民法969条)。
作成には、遺言者と公証人の他に、2名以上の証人の立会いが必要です。公証人は、元裁判官や検察官、法務局長など法律実務に長年携わった法律の専門家であり、全国の公証役場に在籍しています。その公証人が、遺言の内容の適法性や遺言者の意思能力(遺言をするために必要な判断能力)を確認しながら作成するため、法的な不備が極めて少なく、遺言書としての証明力が非常に高いのが大きな特徴です。
公正証書遺言の絶大なメリット
公正証書遺言には、自筆証書遺言と比べて多くの、そして非常に大きなメリットがあります。
-
無効になるリスクが極めて低い 公証人が、遺言の法律的な要件や内容の適法性を確認しながら作成します。また、遺言者の意思能力や、遺言が本人の真意に基づいているかも慎重に確認するため、後日、遺言の方式不備や内容の不明確さ、遺言能力の欠如などを理由に無効とされるリスクが大幅に軽減されます。
-
偽造・変造・紛失の心配がない 作成された公正証書遺言の原本は、原則として公証役場で厳重に保管されます(通常20年間、場合によってはそれ以上)。そのため、第三者による偽造や変造、あるいは遺言者自身や相続人による紛失といった心配がありません。遺言者には、原本の写しである「正本」と「謄本」が交付され、これらを大切に保管することになります。
-
家庭裁判所での「検認」手続きが不要 これが実務上、非常に大きなメリットです。自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要がありますが、公正証書遺言の場合はこの検認が一切不要です。そのため、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現するための手続き(預貯金の解約や不動産の名義変更など)に取り掛かることができます。
-
遺言者の意思能力が争われにくい 公証人は、遺言書作成時に、遺言者が正常な判断能力のもとで遺言をしているかを確認します。そのため、後になって「作成当時は認知症で判断能力がなかった」などとして、遺言の有効性が争われる可能性が、自筆証書遺言に比べて格段に低くなります。
-
内容の実現性が高く、相続手続きがスムーズ 法律の専門家である公証人が関与して作成するため、遺言の内容が法的に明確で、かつ実現可能なものとなります。金融機関や法務局などでの相続手続きの際も、公正証書遺言はその証明力の高さから信頼され、手続きが円滑に進むことが一般的です。
-
字が書けない人や話せない人も作成可能 自筆証書遺言は全文自書が原則ですが、公正証書遺言は、遺言者が署名できない場合でも、公証人がその理由を付記して署名に代えることができます。また、耳が聞こえない方や口がきけない方でも、通訳を介したり、筆談を用いたりするなど、一定の方式に従えば作成が可能です。
これらのメリットから、公正証書遺言は、ご自身の意思を最も確実に実現し、残される家族の負担を軽減するための最良の方法の一つと言えます。
公正証書遺言のデメリット・考慮すべき点
多くのメリットがある公正証書遺言ですが、いくつかのデメリットや事前に考慮しておくべき点もあります。
-
作成に手間と時間がかかる 事前に公証人と打ち合わせをしたり、必要書類を準備したり、証人を選任したりと、自筆証書遺言のように「思い立ったらすぐ作成」というわけにはいきません。ある程度の準備期間が必要です。
-
費用がかかる 公証役場に支払う「公証人手数料」が必要になります。この手数料は、遺言の目的となる財産の価額や、相続人・受遺者の数などによって法律で定められています。また、証人を専門家(行政書士など)に依頼する場合は、別途その費用もかかります。
-
証人2名以上の立会いが必要 公正証書遺言の作成には、信頼できる証人2名以上の立会いが必要です。この証人には、推定相続人(将来相続人になる可能性のある人)、受遺者(遺言で財産をもらう人)及びこれらの者の配偶者や直系血族などはなれないという欠格事由があります(民法974条)。適切な証人を見つける必要があります。
-
内容の秘密保持が完全ではない(証人には知られる) 遺言の内容は、作成に立ち会う証人には知られることになります。ただし、公証人や証人には法律上の守秘義務が課せられていますので、むやみに内容が外部に漏れることはありません。どうしても内容を秘密にしたい場合は、次に解説する「秘密証書遺言」を検討することになります。
これらのデメリットを考慮しても、公正証書遺言が持つメリットは非常に大きいと言えるでしょう。
公正証書遺言作成の一般的な流れ
公正証書遺言を作成する場合の一般的な流れをステップごとに見ていきましょう。
-
ステップ1:遺言内容の検討・決定 まず、誰に、どの財産を、どのように相続させたいのか(または遺贈したいのか)を具体的に決めます。付言事項として家族へのメッセージなどを残すことも可能です。
-
ステップ2:公証役場の選定と相談予約 お近くの公証役場、またはご自身が依頼しやすい公証役場を選び、事前に電話などで相談の日時を予約します。出張作成(遺言者が病気などで公証役場に出向けない場合)に対応してくれる公証役場もあります。
-
ステップ3:必要書類の準備・収集 公証人から指示された必要書類を準備します。主なものは以下の通りですが、事案によって異なります。
- 遺言者の印鑑登録証明書(通常、発行後3ヶ月以内のもの)と実印
- 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
- 財産を相続させる相続人の住民票(または戸籍附票)
- 財産を遺贈する相手(相続人以外)がいる場合は、その方の住民票など
- 不動産を遺言する場合は、その登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資産評価証明書(または固定資産税納税通知書)
- 預貯金や有価証券の場合は、通帳のコピーや残高証明書、証券会社の明細など
- その他、公証人が必要と認める書類
-
ステップ4:公証人との打ち合わせ 準備した書類を持参(または事前に送付)し、公証人と遺言の内容について詳しく打ち合わせを行います。公証人は、遺言者の意思を確認しながら、法律的に問題のない遺言書の原案を作成します。この段階で内容を十分に確認し、修正点があれば伝えます。
-
ステップ5:証人の手配 証人2名以上を手配します。知人や友人に依頼することも可能ですが、前述の欠格事由に該当しないか確認が必要です。適当な人が見つからない場合は、公証役場で紹介してもらえることもありますが、有料となるのが一般的です。また、行政書士や弁護士などの専門家に証人を依頼することも可能です。
-
ステップ6:遺言書作成当日 指定された日時に、遺言者、証人2名が公証役場に集まります(公証人が出張する場合はその場所で)。
- 遺言者が、公証人と証人の面前で、遺言の趣旨を口頭で伝えます(口授)。
- 公証人がそれを筆記し、遺言者と証人に読み聞かせるか、閲覧させます。
- 遺言者と証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押します。
- 最後に公証人が、その証書は法律に定める方式に従って作成したものである旨を付記して、これに署名し、印を押します。
-
ステップ7:遺言書(正本・謄本)の受領と原本の保管 作成された公正証書遺言の原本は公証役場で厳重に保管されます。遺言者には、原本と同じ効力を持つ「正本」と、写しである「謄本」が交付されます。これらを大切に保管します。
公正証書遺言の作成費用(公証人手数料)の目安
公正証書遺言の作成には、公証人に支払う手数料がかかります。この手数料は、「公証人手数料令」という政令に基づいており、主に遺言の目的となる財産の価額に応じて算出されます。
具体的な手数料は以下の要素によって変わってきます。
- 相続または遺贈させる財産の価額の合計
- 相続人または受遺者の数
- 全体の財産が1億円以下の場合は、遺言加算として11,000円が加算される
- 病床などへの出張が必要な場合は、通常の手数料が1.5倍になり、日当や交通費が別途かかる
例えば、財産価額が3,000万円で、1人の相続人に全て相続させる場合の基本手数料は29,000円、これに遺言加算11,000円が加わり合計40,000円、といった具合です。財産の価額や内容が複雑な場合は、事前に公証役場に見積もりを依頼することをお勧めします。
費用はかかりますが、後々のトラブルを回避できる可能性や、検認手続きが不要になることなどを考えれば、十分にその価値はあると言えるでしょう。
公正証書遺言作成における行政書士の強力なサポート
公正証書遺言の作成は、ご自身で直接公証役場とやり取りすることも可能ですが、手続きが煩雑に感じられたり、どのような内容にすればよいか悩んだりすることも多いでしょう。そのような場合、行政書士が強力なサポーターとなります。
-
遺言内容に関するコンサルティング・アドバイス まず、遺言者ご本人のご意思やご希望、家族構成、財産状況などを丁寧にヒアリングします。その上で、法的に問題がなく、かつご本人の想いを最大限に実現できるような遺言内容を一緒に検討し、具体的なアドバイスを行います。
-
必要書類の収集代行 戸籍謄本、住民票、不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書など、公正証書遺言の作成に必要な多くの書類の収集を代行いたします。これにより、皆様の手間を大幅に削減できます。
-
公証人との事前調整・打ち合わせ代行 遺言の原案作成や、公証人との事前打ち合わせ、必要書類の提出などを、ご依頼者に代わって(または同行して)行います。これにより、公証人とのやり取りがスムーズに進み、作成までの時間を短縮できます。
-
信頼できる証人としての立会い 行政書士は、法律により守秘義務が課せられた国家資格者であり、公正証書遺言の証人として適格です。ご親族やご友人に証人を依頼しにくい場合や、適当な方が見つからない場合に、安心して証人をお任せいただけます(別途、証人としての費用が発生します)。
-
遺言執行者への就任 遺言の内容を確実に実現するために、遺言執行者として行政書士を指定していただくことも可能です。その場合、相続開始後、責任をもって遺言の執行業務(財産目録の作成、預貯金の解約、不動産の名義変更の準備、相続人への財産の分配など)を行います。
行政書士に依頼することで、時間的・精神的な負担を軽減し、法的に有効で、かつご自身の想いがしっかりと込められた公正証書遺言を、よりスムーズに、より確実に作成することができます。
まとめ:安心と確実性を求めるなら公正証書遺言
今回は、最も安全で確実な遺言方式とされる「公正証書遺言」について解説しました。
- 公正証書遺言は、公証人が作成に関与するため、無効になるリスクが極めて低く、偽造・変造・紛失の心配もない。
- 相続開始後の家庭裁判所での検認手続きが不要で、相続手続きがスムーズに進む。
- 作成には手間や費用、証人が必要となるが、それ以上の安心と確実性が得られる。
- 行政書士は、公正証書遺言作成の相談から必要書類の収集、公証人との調整、証人としての立会い、遺言執行まで、幅広くサポートできる。
ご自身の最後の意思を、間違いなく、そして残される方々の負担をできるだけ軽くして伝えたいと願うのであれば、公正証書遺言は最も適した選択肢の一つです。
「自分にはどんな遺言が良いのか分からない」「公正証書遺言を作りたいけど、何から始めれば…」など、遺言に関する疑問やお悩みがあれば、どうぞお気軽に行政書士にご相談ください。
次回は、第13回「遺言書の種類③:秘密証書遺言 ~内容を秘密にしたい場合~」と題して、遺言の内容を秘密にしたままその存在を公証人に証明してもらう、少し特殊な遺言方式について解説していきます。

