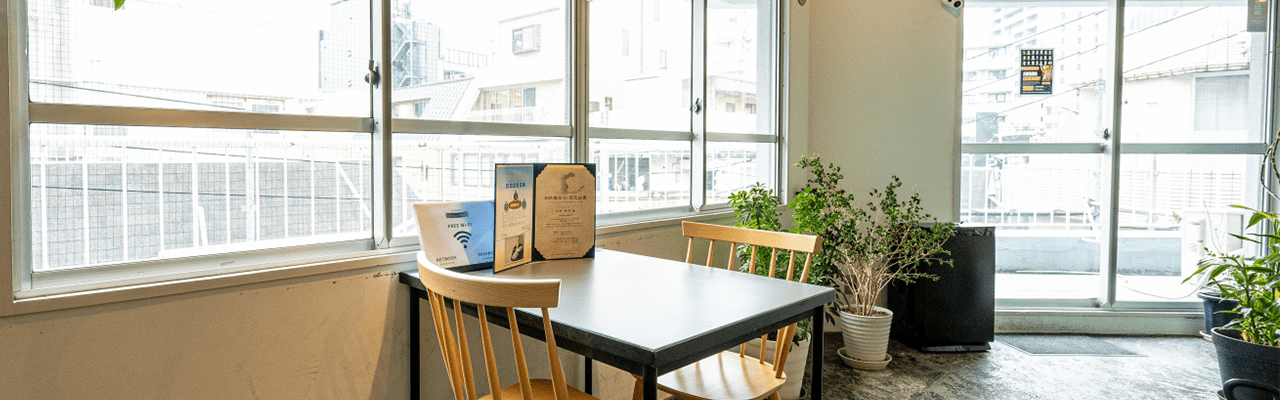
相続セミナー 第13回:遺言書の種類③:秘密証書遺言~内容を秘密にしたい場合~
「遺言書は作りたいけど、その内容を誰にも知られたくない…でも、自分で保管するのは不安…何か良い方法はないの?」
これまでの相続セミナーでは、ご自身で手軽に作成できる「自筆証書遺言」(第11回)と、公証人が関与し最も確実性の高い「公正証書遺言」(第12回)について詳しく解説してきました。それぞれにメリットとデメリットがあり、ご自身の状況や希望に合わせて選択することが大切です。
今回は、遺言書の種類の3つ目として、少し特殊な方式である「秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)」をご紹介します。この遺言方式は、その名の通り、遺言の内容を公証人や証人にさえも秘密にしたまま、遺言書の存在だけを公的に証明してもらうことができるという特徴があります。
しかし、この秘密証書遺言は、手続きがやや複雑で、注意すべき点も多いため、利用を検討する際にはその内容を正確に理解しておく必要があります。この記事では、秘密証書遺言とはどのようなものか、メリットとデメリット、作成の手順、そしてどのような場合に適しているのかを詳しく解説していきます。
秘密証書遺言とは?~内容を隠して存在を証明~
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書を作成し、それに署名・押印した後、その遺言書を封筒に入れて封をし、同じ印鑑で封印します。そして、その封書を公証人1人と証人2名以上の前に提出し、「これは自分の遺言書である」旨と、「これを書いた筆者の氏名と住所」を申述します。公証人は、その封紙に遺言者が提出した日付と遺言者の申述内容を記載し、その後、遺言者、証人、公証人がそれぞれその封紙に署名・押印するという方式の遺言です(民法970条)。
この方式の最大のポイントは、遺言書の内容そのものは、作成者である遺言者以外には誰にも(公証人や証人にも)知られることがない、という点です。公証役場では、遺言書を封入した封紙の控えを保管するわけではなく、封紙に記載された内容(提出日や申述事項)の記録が残る形となります。遺言書本体(封書)は遺言者が持ち帰り、自分で保管します。
なお、遺言書の本文は、自筆である必要はなく、パソコンで作成したり、第三者に代筆してもらったりすることも可能です。ただし、遺言書への署名は必ず遺言者本人が自署しなければなりません。
秘密証書遺言のメリット
秘密証書遺言には、以下のようなメリットが考えられます。
-
遺言の内容を秘密にできる これが最大のメリットです。公正証書遺言では証人に内容が知られますし、自筆証書遺言でも保管状況によっては他人の目に触れる可能性がありますが、秘密証書遺言では、封印された状態で手続きを行うため、遺言の具体的な内容を公証人や証人にさえ知られることなく作成できます。プライバシーを最大限に守りたいと考える方にとっては魅力的な点でしょう。
-
偽造・変造のリスクが比較的低い(封印と公証人の関与) 遺言書が封印され、その封紙に公証人と証人が署名押印するため、自筆証書遺言を単に自宅で保管する場合に比べて、内容の偽造や変造のリスクは軽減されると考えられます。封印が破られていれば、その事実が明らかになります。
-
遺言書の存在を公的に証明できる 公証役場で手続きを行うため、「遺言書を作成し、公証役場に提出した」という事実が公的に記録されます。これにより、遺言書の存在自体が後日不明になるというリスクをある程度避けることができます(ただし、遺言書本体の紛失リスクは残ります)。
-
署名以外は代筆やパソコン作成も可能 自筆証書遺言は全文自書が原則ですが、秘密証書遺言の本文は、パソコンでの作成や、手が不自由な場合に第三者による代筆も認められています。これにより、自筆が困難な方でも作成しやすいという側面があります(ただし、遺言書への署名は必ず遺言者本人が行わなければなりません)。
秘密証書遺言のデメリットと多くの注意点
メリットがある一方で、秘密証書遺言には多くのデメリットや注意すべき点があり、これらを十分に理解しないまま選択すると、期待した効果が得られないばかりか、かえって問題が生じる可能性もあります。
-
方式不備で無効になるリスクが高い 秘密証書遺言は、法律で定められた方式が非常に厳格かつ複雑です。
- 遺言書本体への署名・押印
- 遺言書を封筒に入れ、遺言書に用いた印鑑と同じ印鑑で封印すること
- 公証人および証人2名以上への申述内容(自己の遺言書である旨、筆者の氏名・住所)
- 封紙への公証人による記載、および遺言者・証人・公証人の署名押印 これらの手続きの一つでも不備があったり、法律の要件を満たしていなかったりすると、秘密証書遺言としては無効になってしまいます。ただし、方式に不備があっても、自筆証書遺言の要件(全文自書、日付自書、氏名自書、押印)を満たしていれば、自筆証書遺言として有効になる可能性はあります。
-
遺言内容の有効性・実現性は保証されない 公証人は遺言書の「内容」については一切関与しません。そのため、遺言書に書かれた内容が、
- 法律に違反していたり(例:公序良俗に反する内容など)
- 遺留分を著しく侵害していて、後日紛争の原因となったり
- 財産の記載が不正確で特定できなかったり
- 実現不可能な内容だったり しても、そのまま秘密証書遺言として成立してしまいます。内容に関する専門家のアドバイスがないため、意図した通りに遺言の効力が生じないリスクがあります。
-
遺言書本体の紛失・隠匿のリスクは残る 公正証書遺言とは異なり、秘密証書遺言の本体(封書)は、手続き後に遺言者自身が持ち帰って保管します。そのため、自筆証書遺言と同様に、遺言者自身が保管場所を忘れてしまったり、相続開始後に発見されなかったり、あるいは一部の相続人によって隠匿されたりするリスクが依然として残ります。公証役場には、遺言書を提出したという記録は残りますが、遺言書そのものが保管されるわけではありません。
-
家庭裁判所での「検認」手続きが必ず必要 これも大きなデメリットの一つです。公正証書遺言の場合は不要ですが、秘密証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所に提出して「検認」の手続きを経なければなりません(民法1004条)。検認手続きには、相続人全員への通知や、戸籍謄本などの多くの書類収集が必要となり、時間と手間がかかります。この点は自筆証書遺言(法務局保管制度を利用しない場合)と同様です。
-
作成費用がかかる 自筆証書遺言(自分で作成する場合)と異なり、公証役場に支払う手数料が必要です。秘密証書遺言の公証人手数料は、原則として一律11,000円と定められています。また、証人を専門家(行政書士など)に依頼した場合には、別途その謝礼も必要になります。
-
実際に利用される件数が少ない 上記のようなデメリットや手続きの複雑さから、秘密証書遺言は、他の遺言方式(自筆証書遺言や公正証書遺言)に比べて、実際に利用される件数は非常に少ないのが現状です。そのため、手続きに不慣れな専門家もいる可能性があり、注意が必要です。
秘密証書遺言作成の一般的な流れ
秘密証書遺言を作成する場合の一般的な流れは以下の通りです。
-
ステップ1:遺言書の作成・署名・押印 まず、遺言者本人が遺言の内容を記載した書面(遺言書)を作成します。前述の通り、パソコン作成や代筆も可能ですが、必ず遺言者本人が署名し、押印します。
-
ステップ2:遺言書の封印 作成した遺言書を封筒に入れ、しっかりと封をします。そして、その封じ目に、遺言書本体に押したものと同じ印鑑で押印(封印)します。
-
ステップ3:証人2名以上の手配 公正証書遺言と同様に、信頼できる証人2名以上を手配します。推定相続人や受遺者などは証人になれません。
-
ステップ4:公証役場での手続き 遺言者本人が、手配した証人2名以上と共に公証役場へ出頭します。
- 封印した遺言書(封書)を公証人に提出します。
- 公証人および証人の前で、「これは自己の遺言書である」旨と、「その遺言書を書いた筆者の氏名および住所」(代筆の場合は代筆者の氏名・住所)を申述します。
- 公証人が、その封紙に、遺言書を提出した日付および遺言者の申述内容を記載します。
- その後、遺言者本人、証人2名以上、そして公証人が、それぞれその封紙に署名し、押印します。
-
ステップ5:遺言書(封書)の保管 上記の手続きが完了すると、封印・署名押印された遺言書(封書)は遺言者本人に返還されます。遺言者はこれを持ち帰り、自分で大切に保管します。
どのような場合に秘密証書遺言を検討する?
これまでの説明で、秘密証書遺言は手続きが複雑でデメリットも多いことがお分かりいただけたかと思います。では、どのような場合にこの方式を検討する余地があるのでしょうか。
- 遺言の内容を絶対に誰にも知られたくないが、遺言書の存在だけは公的に明らかにしておきたい場合: これが秘密証書遺言の最大の存在意義と言えるかもしれません。
- 自筆で全文を書くのは困難だが、公正証書遺言のように内容を公証人や証人に知られたくない場合: 署名さえできれば、本文はワープロや代筆が可能です。
- 費用を抑えつつ、自筆証書遺言よりは偽造・変造リスクを少しでも減らしたいと考える場合: ただし、検認が必要なことや内容の有効性が保証されない点を考慮すると、費用対効果が高いとは言えないかもしれません。
しかし、多くの場合、遺言の内容を秘密にする必要性がそれほど高くないのであれば、より安全確実な「公正証書遺言」を選択するか、あるいは費用を抑えたいのであれば「自筆証書遺言(法務局保管制度の利用を推奨)」を選択する方が、現実的なメリットが大きいと言えるでしょう。
秘密証書遺言と行政書士の関わり
秘密証書遺言の作成を検討される場合でも、行政書士がお手伝いできることがあります。
- 制度説明と他の遺言方式との比較検討: 秘密証書遺言の法的な要件、手続きの流れ、メリット・デメリットを詳しくご説明し、ご依頼者の状況やご希望に応じて、自筆証書遺言や公正証書遺言といった他の方式と比較検討し、最適な選択ができるようアドバイスします。
- 遺言書本文の作成サポート: 遺言者ご本人の意思に基づき、法的に問題のない、明確な内容の遺言書本文の作成をサポートします。(最終的な署名は必ず遺言者本人が行います。)
- 公証役場での手続きサポート: 公証役場への提出書類の準備や、手続きの流れについてご案内します。また、信頼できる証人が見つからない場合には、行政書士が証人として立ち会うことも可能です(別途費用)。
- 将来の検認手続き申立書の作成支援: 相続開始後、必要となる家庭裁判所への検認申立書の作成を支援します。
秘密証書遺言は、その特性をよく理解した上で選択する必要があるため、まずは専門家である行政書士にご相談いただくことをお勧めします。
まとめ:秘密保持と引き換えにリスクも伴う選択肢
今回は、遺言書の種類の一つである「秘密証書遺言」について解説しました。
- 秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られずに作成し、その存在を公証役場で証明してもらえる方式。
- 署名以外はパソコン作成や代筆も可能という柔軟性がある。
- しかし、方式不備で無効になるリスク、内容の有効性が保証されないリスク、紛失リスク、そして検認手続きが必要という多くのデメリットがある。
- 利用件数は少なく、メリットが限定的であるため、選択は慎重に行うべき。
遺言の内容をどうしても秘密にしたいという強いご希望がある場合には検討の余地がありますが、多くの場合、他の遺言方式の方がより安全かつ確実と言えるでしょう。ご自身の状況や希望をよく考え、専門家とも相談しながら、最適な遺言の方式を選択することが大切です。
次回は、第14回「自筆証書遺言、法務局保管制度の活用法 ~メリットと手続き~」と題して、自筆証書遺言のデメリットをカバーし、より安全性を高めることができる「自筆証書遺言書保管制度」について詳しく解説していきます。

