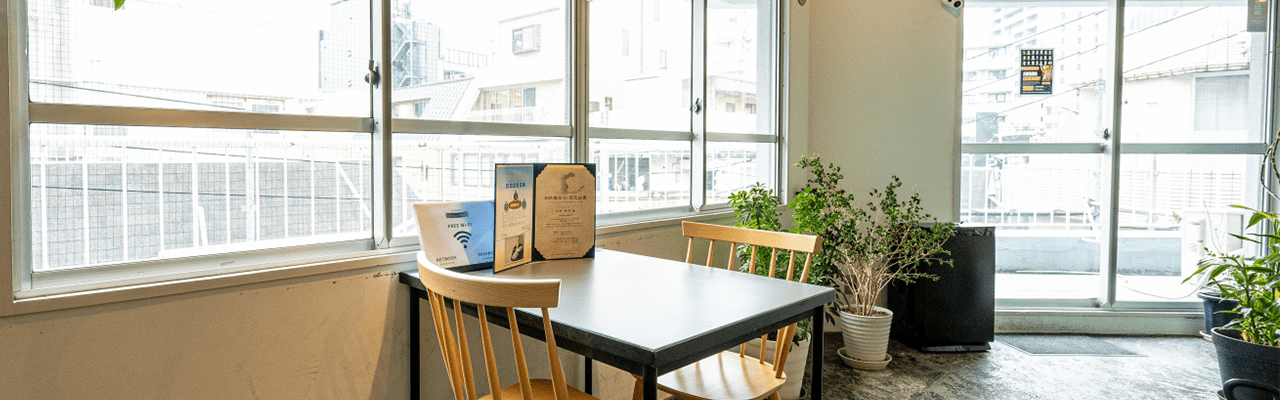
相続セミナー 第22回:なぜ今、家族信託が注目されるのか? ~超高齢社会の課題解決策~
「家族信託って、どうして最近よく聞くようになったの?」「何か特別な理由があるんだろうか…」
前回の第21回ブログでは、【第3部】のスタートとして、「家族信託」の基本的な仕組みや登場人物について解説しました。財産を信頼できる人に託し、特定の目的のために管理・承継してもらうという、オーダーメイドの財産管理・承継の形であることをご理解いただけたかと思います。
では、なぜこの「家族信託」という仕組みが、近年これほどまでに大きな注目を集めているのでしょうか。それは単なる一時的なブームなのではなく、現代の日本社会が抱える深刻な課題、特に「超高齢社会」がもたらす様々な問題に対する、有効な解決策の一つとして大きな期待が寄せられているからなのです。
今回のセミナーでは、家族信託がなぜ今、これほどまでに必要とされ、注目されているのか、その背景にある社会的な課題を具体的に紐解きながら、家族信託がそれらの課題解決にどのように貢献できるのかを詳しく解説していきます。
現代日本が直面する大きな課題~超高齢社会の現実~
現在の日本は、世界でも類を見ない速さで高齢化が進行し、「超高齢社会」と呼ばれる状況にあります。この超高齢社会は、私たちの生活や財産管理、そしてその承継に、以下のような大きな影響を及ぼしています。
-
平均寿命の延伸と「健康寿命」とのギャップの拡大: 医療の進歩などにより平均寿命は延び続けていますが、一方で、介護などを必要とせず自立して生活できる期間を示す「健康寿命」との間には、依然として数年~十数年のギャップがあります。このギャップの期間は、判断能力や身体能力の低下により、ご自身での財産管理が難しくなる可能性が高まります。
-
認知症患者数の急増: 高齢化に伴い、認知症を患う方の数は年々増加しており、今後もさらに増え続けると予測されています。認知症になると、ご自身の意思で契約を結んだり、財産を処分したりすることが法的に困難になる場合があります。
-
核家族化の進行と「おひとりさま」世帯の増加: かつてのような多世代同居の家族は減少し、核家族化が進んでいます。また、生涯未婚の方や、配偶者と死別・離別した後に一人で暮らす「おひとりさま」の高齢者も増加傾向にあります。これにより、いざという時に頼れる家族が身近にいなかったり、財産管理や承継について相談できる相手がいなかったりするケースが増えています。
これらの社会的な変化は、従来の相続対策や財産管理の方法だけでは対応しきれない、新たな課題を生み出しているのです。
課題1:認知症による「資産凍結」リスクの深刻化
家族信託が注目される最大の理由の一つが、この「認知症による資産凍結リスク」への対応です。
- 資産凍結とは? 認知症などにより本人の意思能力(判断能力)が著しく低下したと判断されると、その方が所有する預貯金口座からの現金の引き出し(生活費や介護費用、医療費など)、不動産の売却や賃貸契約、株式の売買といった法律行為が、原則としてできなくなってしまいます。これを「資産凍結」といいます。たとえ家族であっても、本人の財産を自由に動かすことはできません。
- 具体的な困りごと:
- 親の介護費用や医療費を、親の預金から支払いたいのに引き出せない。
- 親が施設に入所するため、実家を売却して費用に充てたいが、親に判断能力がないため売却できない。
- 相続税対策のために生前贈与を計画していたが、本人の判断能力低下により実行できない。
- 成年後見制度の限界: このような場合に利用できる法的な制度として「成年後見制度」がありますが、この制度はあくまで「本人の財産を保護する」ことが主眼であり、家庭裁判所の監督のもとで後見人が財産管理を行うため、財産の積極的な運用や柔軟な組み換え(例えば、より収益性の高い不動産への買い替えや、相続対策のための資産処分など)には制約が多く、手続きも煩雑です。また、必ずしも家族が後見人に選任されるとは限らず、専門職後見人への報酬も発生します。
家族信託は、この「資産凍結」リスクに対する有効な予防策となり得ます。 本人が元気で判断能力がしっかりしているうちに、信頼できる家族(例えば子など)を受託者として信託契約を結び、財産の管理・処分権限を託しておけば、将来、本人が認知症などで判断能力を失ったとしても、受託者は信託契約で定められた目的に従って、引き続き本人のために柔軟な財産管理(預金の引き出し、不動産の売却や賃貸、必要な契約の締結など)を継続することができます。これにより、本人の生活を守り、家族の負担を軽減することが可能になるのです。
課題2:円滑な「財産承継・事業承継」の難しさ
従来の相続対策の中心であった「遺言」だけでは対応しきれない、より複雑で長期的な財産承継や事業承継のニーズが高まっています。
- 二次相続以降の承継先の指定(想いのリレー): 遺言では、原則として自分の次の相続人への財産の渡し方しか指定できません。しかし、「自分が亡くなったら、まずは長年連れ添った妻に財産を遺し、妻が安心して生活できるようにしたい。そして、妻も亡くなったら、残った財産は子供たちに相続させたい」といったように、数世代にわたる財産の承継の希望(いわゆる「後継ぎ遺贈型」の想い)を持つ方も少なくありません。
- 障がいのある子の将来の生活保障(親なき後問題): 障がいのあるお子さんを持つ親御さんにとって、自分たちが亡くなった後、子供が経済的に困窮せず、安心して生活を続けられるようにすることは、何よりの願いです。遺言で財産を残すことはできますが、その財産をお子さん自身が適切に管理できるか、あるいは他の親族が継続的にサポートしてくれるかといった不安が残ります。
- 中小企業経営者の高齢化と事業承継問題: 多くの中小企業では、経営者の高齢化が進み、後継者への円滑な事業承継が大きな課題となっています。後継者に自社株式や事業用資産をスムーズに集中させ、経営の安定性を確保し、従業員の雇用を守るためには、計画的な対策が必要です。遺言だけでは、他の相続人からの遺留分請求などで株式が分散してしまうリスクも考えられます。
家族信託は、これらの多様な承継ニーズにも柔軟に対応できます。
- 受益者連続型信託: 信託契約の中で、最初の受益者(例えば委託者本人)が亡くなった後の次の受益者(例えば配偶者)、さらにその次の受益者(例えば子)というように、受益権をリレー形式で承継させていく設計が可能です。これにより、遺言では難しかった長期的な財産承継のコントロールが実現できます。
- 福祉型信託: 障がいのあるお子さんを受益者とし、信頼できる親族や専門家を受託者として、親御さんの亡き後も継続的に生活費や療養費を給付し、身上監護(生活の見守りなど)の役割を担ってもらうような信託を設計できます。
- 事業承継信託: 経営者が持つ自社株式を後継者である受託者に信託し、経営権(議決権)は後継者に集約しつつ、配当などの経済的利益は当面経営者(受益者)が受け取る、といった設計が可能です。これにより、経営の安定化とスムーズな権限移譲を図ることができます。
課題3:「おひとりさま」や子のいない夫婦の「もしも」への備え
生涯未婚の方や、配偶者に先立たれたり離婚したりして一人で暮らす「おひとりさま」、また子供のいないご夫婦も増加しています。このような方々にとっては、
- 自身の判断能力が低下した際の財産管理や身上監護
- 亡くなった後の財産の処分や整理、葬儀や納骨などの死後事務 を誰に託すのか、という問題がより切実になります。遺言書で死後の財産の行き先は指定できますが、生前の財産管理や判断能力低下後のサポートには対応できません。
家族信託は、このような状況にも対応できる可能性があります。 信頼できる甥姪や友人、あるいは行政書士や弁護士などの専門家、一般社団法人などを受託者や「信託監督人(受託者の業務を監督する人)」として関与させることで、生前の財産管理から、判断能力低下後の生活支援、そして亡くなった後の財産処分や寄付、死後事務の実行までを、ご自身の意思に沿って託す仕組みを設計することができます。
課題4:不動産の共有問題と空き家の増加
相続が発生すると、不動産が複数の相続人の共有名義になることがよくあります。共有名義の不動産は、その保存・管理・処分(売却など)を行う際に、原則として共有者全員の同意が必要となるため、意思決定が難しく、活用もされずに放置され、結果として管理不全な空き家が増加する一因ともなっています。
家族信託は、この不動産の共有問題の解決にも役立ちます。 共有名義の不動産を、共有者全員が委託者となって、代表者(例えば共有者の一人や専門家)を受託者として信託することで、その不動産の管理・処分権限を受託者に集約することができます。これにより、賃貸に出したり、売却したりといった意思決定や実行がスムーズになり、不動産の有効活用や円滑な現金化が可能になります。
家族信託が注目される本質的な理由~「想い」を「生前」から「柔軟」に~
ここまで見てきたように、家族信託が注目される背景には、超高齢社会がもたらす様々な現実的な課題があります。そして、家族信託がこれらの課題に対する有効な選択肢となり得るのは、それが以下のような本質的な特徴を持っているからです。
- 「本人の意思」を尊重できる: 誰に、何を、どのように託すか、本人が元気なうちに自らの意思で決められる。
- 「生前の元気なうち」から対策を始められる: 判断能力が低下する前に準備することで、将来の不安に備えられる。
- 「柔軟な」財産管理・承継が可能: 契約内容をオーダーメイドで設計できるため、個々の家庭の状況や希望に合わせたきめ細やかな対応ができる。
- 「予防法務」としての効果が高い: 問題が起きてしまってからでは対応が難しいことも、事前に手を打つことで回避できる可能性が高まる。
家族信託は、従来の遺言や成年後見制度ではカバーしきれなかった「隙間」を埋め、より多くの人々の「想い」を実現するための、新しい時代の財産管理・承継のツールと言えるでしょう。
行政書士と家族信託~社会課題解決への専門家としての貢献~
私たち行政書士は、契約書作成の専門家であり、また相続や遺言に関する深い知識と経験を有しています。家族信託という新しい制度が注目される中で、これらの社会課題に直面する方々に対し、有効な選択肢として家族信託を提案し、その設計から実行までをサポートさせていただくことは、行政書士の重要な社会的役割の一つであると考えています。
- 個々のご家庭の状況や、ご本人はもちろんご家族の皆様の想いを丁寧にヒアリングし、本当に家族信託が適しているのか、どのような設計が最適なのかを一緒に考えます。
- 複雑な法律関係や権利義務を分かりやすくご説明し、ご家族全員が納得して進められるよう、オーダーメイドの信託契約書作成を支援します。
- 必要に応じて、弁護士、司法書士、税理士といった他の専門家とも緊密に連携し、法務・税務の両面から最適な信託の実現を包括的にサポートします。
認知症による資産凍結対策、円滑な事業承継、障がいのあるお子さんの将来設計、おひとりさまの終活支援など、家族信託が貢献できる分野は多岐にわたります。
まとめ:家族信託は、超高齢社会の希望の光となり得るか
今回は、「なぜ今、家族信託が注目されるのか」というテーマで、その背景にある超高齢社会の課題と、それに対する家族信託の可能性について解説しました。
- 認知症による資産凍結、円滑な財産承継の困難、おひとりさまの増加といった現代社会の切実な課題に対し、家族信託は有効な解決策を提示できる可能性がある。
- 本人の意思を尊重し、生前から柔軟かつ長期的な財産管理・承継を実現できる点が、家族信託の大きな魅力。
- これらの課題に心当たりがある方は、選択肢の一つとして家族信託を検討する価値がある。
家族信託は、まだ発展途上の制度ではありますが、私たちの未来をより安心で豊かなものにするための、大きな可能性を秘めていると言えるでしょう。
次回は、第23回「家族信託の登場人物~委託者・受託者・受益者とは?~」と題して、家族信託を構成する上で欠かせない3つの役割である「委託者」「受託者」「受益者」について、それぞれの立場や権利義務をさらに詳しく掘り下げて解説していきます。

