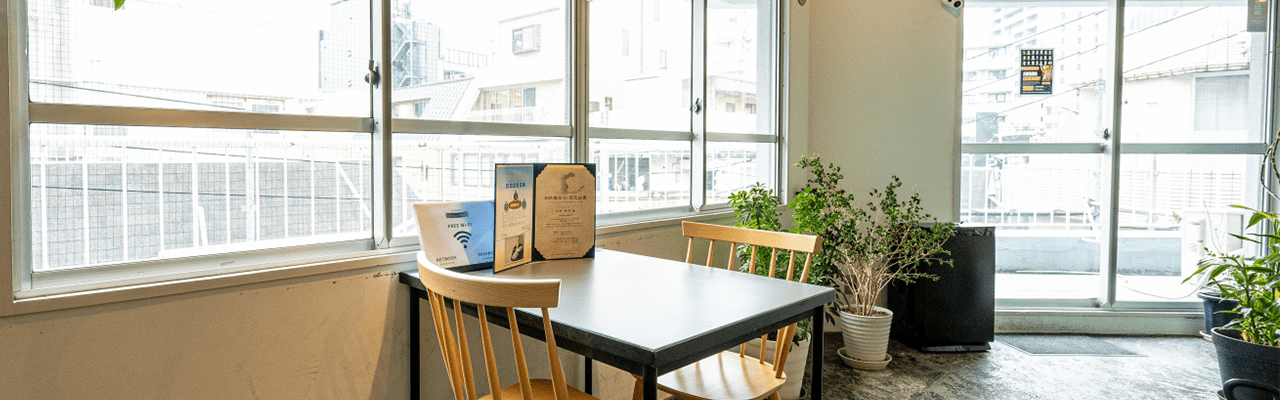
相続セミナー第48回: 生前贈与の活用と注意点 ~暦年贈与と相続時精算課税制度~
「将来、子どもたちにかかる相続税の負担を少しでも軽くしてあげたい」「元気なうちに、孫の教育資金やマイホーム資金を援助したい」「自分の財産は、自分の意思で、確実にこの人に渡したい」こうしたお考えをお持ちの方は少なくないでしょう。その有効な手段の一つとして注目されるのが「生前贈与」です。
今回のブログでは、この生前贈与について、そのメリット・デメリット、そして代表的な制度である「暦年贈与(れきねんぞうよ)」と「相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)」の仕組みや活用法、さらに2024年1月1日から大きく変わった改正点も含めて、分かりやすく解説していきます。生前贈与を上手に活用するための注意点や、私たち行政書士が贈与契約書の作成や遺言との関連でどのようにサポートできるかについても触れていきますので、ぜひ最後までご覧ください。
生前贈与とは何か?なぜ活用されるのか?
まず、「生前贈与」とは何か、その基本的な定義から見ていきましょう。
生前贈与とは、文字通り、個人が生きている間に、ご自身の財産を他の人(贈与者から見て受贈者といいます)に無償で与えることをいいます。贈与は契約の一種であり、贈与者が「あげます」という意思表示をし、受贈者が「もらいます」という意思表示をすることで成立します。
生前贈与が活用される主な目的としては、以下のようなものが挙げられます。
- 相続税対策: 将来発生する相続税の課税対象となる財産を、生前のうちに計画的に減らしておくことで、相続税の負担を軽減することを目的とします。
- 早期の財産移転: 子や孫の結婚、住宅購入、事業開始、教育資金など、受贈者が必要とするタイミングで資金を援助することができます。
- 特定の意思の実現: 遺言だけでなく、生前贈与によっても、自分の財産を確実に特定の人に渡したいという意思を実現できます。
- 遺産分割トラブルの予防: あらかじめ特定の財産を生前に贈与しておくことで、相続発生時の遺産分割協議の対象財産を減らし、相続人間の争いをある程度回避できる可能性があります。(ただし、やり方によっては逆にトラブルの原因になることもあります。)
生前贈与のメリット・デメリット
生前贈与には多くのメリットがありますが、同時にデメリットや注意すべき点も存在します。両方を理解した上で、慎重に検討することが大切です。
【生前贈与のメリット】
- 計画的な財産移転が可能: いつ、誰に、何を、どれだけ渡すかを、贈与者が自分の意思でコントロールしながら計画的に行うことができます。
- 受贈者のタイミングで活用可能: 受贈者は、贈与された財産を、住宅購入や教育資金など、自身のライフプランに合わせて必要な時期に活用できます。
- 相続税の節税効果(制度を上手に使えば): 非課税枠をうまく利用したり、将来値上がりしそうな財産を早めに移転したりすることで、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
- 感謝の気持ちを直接伝えられる: 生きているうちに財産を渡すことで、受贈者へ直接感謝の気持ちを伝えたり、喜ぶ顔を見たりすることができます。
- 遺産分割の対象から外せる可能性: 原則として、生前贈与された財産は遺産分割の対象にはなりません(ただし、特別受益や遺留分の問題は別途考慮が必要です)。
【生前贈与のデメリット・注意点】
- 贈与税がかかる可能性: 贈与額が基礎控除額を超える場合や、特例の要件を満たさない場合には、高率な贈与税が課されることがあります。
- 原則として取り消せない: 一度有効に成立した贈与は、原則として一方的に取り消すことはできません。
- 不動産の場合、諸費用がかかる: 不動産を贈与する場合、贈与税のほかに登録免許税(名義変更の登記費用)や不動産取得税が課されます。これらは相続で取得する場合よりも税率が高くなることがあります。
- 相続税対策のつもりが逆効果になることも: 税制は複雑で、頻繁に改正されます。知識不足のまま行うと、期待した節税効果が得られないばかりか、かえって税負担が増えるケースもあります。
- 遺留分侵害のリスク: 特定の相続人に偏った生前贈与を行うと、他の相続人の遺留分(法律で保障された最低限の相続分)を侵害し、相続発生後にトラブル(遺留分侵害額請求)の原因となることがあります。
- 贈与者の生活資金の確保: 将来の生活設計を考えず、老後の生活資金まで贈与してしまうと、自身の生活が困窮するリスクがあります。
代表的な生前贈与の制度①:暦年贈与(れきねんぞうよ)
生前贈与の最も基本的な方法として広く知られているのが「暦年贈与」です。
【暦年贈与の仕組み】 暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額が、受贈者1人あたり110万円以下であれば、贈与税がかからず、税務署への申告も不要という制度です。この110万円を「基礎控除額」といいます。
【暦年贈与の活用方法】 この年間110万円の非課税枠を利用して、毎年コツコツと複数年にわたり、複数の人(例えば、子や孫それぞれ)に贈与を続けることで、非課税でまとまった額の財産を移転できる可能性があります。 例えば、子2人と孫3人の合計5人に、毎年110万円ずつ10年間贈与を続けると、総額で「110万円 × 5人 × 10年 = 5,500万円」もの財産を非課税で移転できる計算になります(ただし、後述の持ち戻しルールに注意が必要です)。
【暦年贈与の注意点】
- 名義預金とみなされるリスク: 親が子の名義で預金口座を作り、そこに入金していても、通帳や印鑑を親が管理し、子がその存在を知らなかったり自由に使えなかったりする場合には、贈与とは認められず、相続発生時に親の財産(名義預金)として扱われるリスクがあります。贈与の事実を明確にするため、贈与契約書を作成し、口座の管理は受贈者自身が行うことが重要です。
- 定期贈与(連年贈与)とみなされるリスク: 例えば、「毎年100万円を10年間にわたって贈与する」という約束を最初からしていたとみなされると、総額1,000万円の贈与を10年で分割して履行しただけと判断され、初年度に1,000万円全額に対する贈与税が課税される可能性があります。これを避けるためには、毎年、その都度贈与契約を結び、贈与の意思を明確にすることが推奨されます。
- 相続開始前一定期間内の贈与の持ち戻し(重要!): 暦年贈与によって贈与税がかからなかった財産であっても、相続開始前一定期間内に行われた贈与については、相続財産に加算して相続税を計算する「生前贈与加算」の対象となります。 **従来は相続開始前「3年以内」**の贈与が対象でしたが、2024年1月1日以降の贈与については、この期間が段階的に「7年以内」に延長されます。この改正は、暦年贈与による相続税対策の効果に大きく影響しますので、十分な理解が必要です。
- 贈与の証拠を確実に残す: 後々のトラブルや税務署からの問い合わせに備え、贈与の事実を証明できる証拠を残しておくことが非常に大切です。
- 贈与契約書の作成: 誰から誰へ、いつ、何を、いくら贈与したのかを明記した書面を作成し、贈与者と受贈者が署名押印します。私たち行政書士は、この贈与契約書の作成を専門的にサポートできます。
- 銀行振込の利用: 現金手渡しではなく、銀行振込を利用することで、お金の流れを客観的に記録できます。
代表的な生前贈与の制度②:相続時精算課税制度
もう一つの代表的な生前贈与の制度が「相続時精算課税制度」です。これは、特定の条件を満たす場合に、生前贈与時の贈与税負担を軽減し、相続発生時にその贈与財産と相続財産を合算して相続税で精算するという仕組みです。
【相続時精算課税制度の仕組み(原則)】
- 対象者: 贈与者は贈与年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母、受贈者は贈与年の1月1日において18歳以上の子または孫です。
- 非課税枠(特別控除): 受贈者ごとに累計で2,500万円までの贈与については、贈与税がかかりません(この2,500万円を「特別控除額」といいます)。
- 超過分への課税: 累計2,500万円を超えた部分については、**一律20%**の贈与税が課されます。
- 相続時の精算: この制度を利用して贈与された財産は、贈与時の価額で、相続発生時に相続財産に全額加算され、相続税が計算されます。その際、既に支払った贈与税額があれば、算出された相続税額から控除されます。
- 一度選択すると暦年贈与に戻れない: この制度を選択すると、その特定の贈与者からの贈与については、その後、暦年贈与の基礎控除(年間110万円)を利用することはできませんでした(※改正点あり)。
【2024年1月1日からの大改正! – 年間110万円の基礎控除創設】
この相続時精算課税制度について、2024年1月1日以降の贈与から非常に大きな改正がありました。それは、上記の2,500万円の特別控除とは別に、新たに年間110万円の基礎控除が創設されたことです。
- 改正後のポイント:
- 相続時精算課税制度を選択した場合でも、毎年110万円までの贈与であれば、贈与税の申告が不要となり、かつ、この年間110万円以下の部分は相続財産への加算も不要となります。
- これにより、相続時精算課税制度の使い勝手が格段に向上し、暦年贈与の生前贈与加算期間の延長(3年から7年へ)を補う選択肢として、より注目されるようになりました。
【相続時精算課税制度のメリット(改正後を踏まえて)】
- 年間110万円の非課税枠の新設: 毎年110万円までなら、贈与税申告不要かつ相続財産への加算なしで確実に財産を移転できます。
- 早期にまとまった財産を移転しやすい: 子や孫の住宅購入資金や開業資金など、まとまった額の資金を早期に贈与したい場合に、2,500万円の特別控除と合わせて活用することで、贈与税の負担を抑えつつ移転できます。
- 将来値上がりが期待される財産の評価額固定: 収益不動産や将来性のある自社株など、相続時には価値が上昇している可能性のある財産を、贈与時の価額で評価して相続財産に加算できるため、節税効果が期待できる場合があります。(ただし、逆に値下がりした場合は不利になるリスクもあります。)
【相続時精算課税制度のデメリット・注意点】
- 暦年課税への変更不可: 一度、特定の贈与者(例:父)からの贈与について相続時精算課税制度を選択すると、その後、その贈与者(父)からの贈与については暦年課税に戻ることはできません(他の贈与者、例えば母からの贈与については暦年課税を選択可能です)。
- 小規模宅地等の特例の適用制限: この制度で贈与された土地は、相続時に相続財産として持ち戻されても、原則として相続税の「小規模宅地等の特例」の対象とならないため、注意が必要です。
- 不動産贈与のコスト: 不動産をこの制度で贈与する場合、登録免許税や不動産取得税は暦年贈与の場合と同様にかかります。
- 贈与財産の値下がりリスク: 贈与された財産が相続時に値下がりしていた場合でも、贈与時の価額で相続税が計算されるため、結果的に不利になる可能性があります。
相続時精算課税制度の選択は、メリットとデメリットを十分に比較し、将来の相続まで見据えた慎重な判断が必要です。税理士などの専門家への相談が不可欠です。
その他の生前贈与の特例(概要)
暦年贈与や相続時精算課税制度のほかにも、特定の目的のための贈与には、期間限定で非課税枠が設けられている特例があります。
- 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置: 父母や祖父母などの直系尊属から、子や孫がマイホームを新築・取得・増改築するための資金援助を受けた場合に、一定の要件を満たせば、最高1,000万円(省エネ等住宅の場合。一般住宅は500万円。2023年末までの措置でしたが、延長・改正の可能性あり)まで贈与税が非課税となる制度です。
- 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置: 父母や祖父母などの直系尊属が、30歳未満の子や孫に対して、教育資金として金融機関に専用口座を開設して一括で拠出した場合に、受贈者1人あたり1,500万円(学校以外の塾や習い事等は500万円)まで贈与税が非課税となる制度です(2026年3月31日まで)。
- 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置: 父母や祖父母などの直系尊属が、18歳以上50歳未満の子や孫に対して、結婚・子育て資金として金融機関に専用口座を開設して一括で拠出した場合に、受贈者1人あたり1,000万円(結婚関係は300万円)まで贈与税が非課税となる制度です(2025年3月31日まで)。
これらの特例は、使途や期間が限定されており、金融機関との契約や税務署への一定の手続きが必要となるため、利用する際には必ず専門家にご相談ください。
生前贈与を活用する際の【超重要】な注意点
どの制度を利用するにしても、生前贈与を有効かつ安全に行うためには、以下の点に十分注意する必要があります。
- 贈与の意思と事実を明確にする(贈与契約書の作成!): 「あげた」「もらった」という当事者間の合意(贈与契約)を明確にするため、必ず贈与契約書を作成しましょう。いつ、誰から誰へ、何を、どのように贈与したのかを具体的に記載し、贈与者と受贈者が署名押印します。これが後のトラブル防止や、税務署への説明資料として極めて重要になります。
- 受贈者自身による財産の管理・支配: 特に預貯金の贈与の場合、受贈者名義の口座に入金するだけでなく、その通帳や印鑑、キャッシュカードを受贈者自身が管理し、自由に使える状態にしておくことが大切です。「名義預金」とみなされないための重要なポイントです。
- 相続税対策としての効果を慎重に検討: 税制は頻繁に改正されます。2024年からの大きな改正(生前贈与加算の7年化、相続時精算課税制度への年間110万円基礎控除導入)は、今後の生前贈与戦略に大きな影響を与えます。最新の情報に基づき、専門家のアドバイスを受けながら慎重に検討しましょう。
- 遺留分への配慮を忘れずに: 特定の人に多額の生前贈与を行うと、他の相続人の遺留分を侵害してしまう可能性があります。遺留分を侵害すると、相続発生後に遺留分侵害額請求という紛争が生じることがあります。遺言書作成と同様に、生前贈与においても遺留分への配慮は不可欠です。
- 他の相続人への説明と理解: 法律上の義務ではありませんが、可能であれば、なぜ特定の生前贈与を行うのか、その理由や想いを他の相続人にも伝えておくことで、将来の無用な憶測や不公平感を和らげ、円満な相続に繋がる可能性があります。
- 贈与者の生活資金を確保する: 良かれと思って行った生前贈与が、ご自身の老後の生活資金を圧迫し、生活に困窮するような事態になっては本末転倒です。無理のない範囲で、計画的に行うことが大前提です。
生前贈与と行政書士・税理士の役割:専門家との連携が鍵
生前贈与の計画・実行には、法務面と税務面の両方からの専門的な検討が欠かせません。
-
行政書士の役割:
- 贈与契約書の作成サポート: 生前贈与の最も基本的な証拠となる贈与契約書の作成を、法的な観点からサポートします。契約内容の明確化、当事者の意思確認、適切な形式での作成など、将来の紛争予防に繋がる書類作成を行います。
- 遺言書作成との関連でのアドバイス: 生前贈与は、遺言による財産承継と密接に関連します。生前贈与の内容と遺言の内容が矛盾しないよう、あるいは補完し合うよう、トータルな視点からアドバイスを提供し、円満な相続実現をサポートします。
- 相続発生時の手続きサポート: 生前贈与があった場合の遺産分割協議において、その事実をどのように考慮するか(特別受益など)、法的な助言や協議のサポートを行います。
- 将来の相続を見据えた情報提供と専門家への橋渡し: 相続全般に関する情報提供を行い、税務に関する専門的な判断が必要な場合には、信頼できる税理士を速やかにご紹介し、スムーズな連携を図ります。
-
税理士の役割:
- 贈与税・相続税の具体的な税額計算とシミュレーション: 暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらが有利か、各種特例を適用した場合の税額はどうなるかなど、具体的な数字に基づいた比較検討を行います。
- 贈与税・相続税の申告書の作成・提出代行。
- 各種特例適用のための手続きサポート。
- 相続税対策全般に関する専門的なコンサルティング。
生前贈与は、メリットも大きい反面、法務・税務の両面で注意すべき点が多い複雑な手続きです。私たち行政書士は、まず法務面からのサポートや全体的なアドバイスを行い、税務の専門家である税理士と緊密に連携することで、ご依頼者様にとって最適な生前贈与の実現をお手伝いします。
まとめ:生前贈与は計画的に!2024年改正も踏まえ専門家へ相談を
今回は、相続対策や早期の財産移転の有効な手段である「生前贈与」について、代表的な制度である「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」を中心に、その仕組み、メリット・デメリット、そして2024年1月1日からの重要な改正点、活用時の注意点などを解説しました。
生前贈与は、上手に活用すれば大きなメリットがありますが、安易な判断は禁物です。特に税制は複雑で変更も多いため、常に最新の情報を把握し、ご自身の状況に合わせて最適な方法を選択する必要があります。贈与契約書の作成といった法的な手続きや、遺留分への配慮も忘れてはなりません。
「うちの場合はどうなんだろう?」「どの制度を使えばいいの?」と少しでも疑問に思われたら、まずは私たち行政書士や税理士といった専門家にご相談ください。計画段階から専門家のアドバイスを受けることが、後悔のない、そして効果的な生前贈与への第一歩です。
次回は、相続に関する様々な困りごとや手続きについて、「誰に相談すれば良いのか?」という疑問にお答えする、相続セミナー第49回「困ったときの相談先 ~行政書士・弁護士・税理士・司法書士の役割分担~」をお届けします。専門家の選び方や、それぞれの得意分野について解説しますので、ぜひご覧ください。

